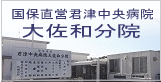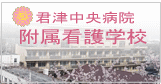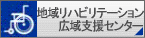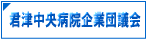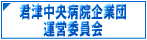病理診断科
診療内容と特徴
当科では、日本病理学会病理専門医の資格を有する3名の常勤病理医と、数名の非常勤病理医が臨床各科から提出された検体に対し、病理診断を行っています。診療科ではありますが、患者さんを前に診療は行っておりません。それでは何をしているかと申しますと、患者さんの体より採取された組織や細胞から作られたガラス標本(プレパラート)を顕微鏡下で診断し、臨床科の医師に情報提供するのが主な仕事です。病理診断は、病気の最終的な診断となり、治療に生かされます。病理診断には、病理組織診、細胞診、病理解剖があります。
- ① 病理組織診:採取された組織を肉眼的あるいは顕微鏡を用いて観察し、組織・細胞の変化をもとに病気を診断します。たとえば、病変が腫瘍なのか炎症なのか、腫瘍であるとすれば良性なのか悪性なのかを診断します。手術で摘出された組織からは、病気の確定診断以外に、病気の進行度の判定、治療の評価や効果判定を行っています。また、手術中に切除範囲を決めるために行われる術中迅速診も行っています。
- ② 細胞診:体腔液や病変部から採取された細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞の有無を調べる補助的な診断です。
- ③ 病理解剖:不幸にしてお亡くなりになられた患者さんに対し、ご遺族の承諾が得られた場合に、病理解剖を行っています。病理解剖では、死に至った病気の全貌を観察し、診断が正しかったか、治療効果や副作用はどうであったか、死因は何であるか、などを調べます。そして、臨床病理検討会 (clinicopathological conference: CPC)という臨床医・病理医が同席したカンファレンスにおいて詳細に検討し、医療の質の向上に役立てています。
診療スタッフ紹介
| 氏名 | 野口 寛子 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局病理診断科部長、科長 | |
| 出身校(卒業年) | 浜松医科大学(平成7年) 医学博士(札幌医科大学) |
|
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医・学術評議員 日本臨床細胞学会専門医・研修指導医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 |
| 氏名 | 木原 淳 |  |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局病理診断科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 東京医科歯科大学(平成16年) 医学博士(東京医科歯科大学) |
|
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医・学術評議員 日本病理学会分子病理専門医 日本臨床細胞学会専門医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 |
| 氏名 | 板垣 信吾 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局病理診断科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 自治医科大学(平成19年) | |
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医 日本病理学会分子病理専門医 日本臨床細胞学会専門医 日本臨床検査医学会臨床検査管理医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 |
非常勤
| 氏名 | 矢澤 卓也 | |
|---|---|---|
| 職名 | 獨協医科大学病理学主任教授 | |
| 出身校(卒業年) | 筑波大学(昭和63年) 医学博士(筑波大学) | |
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 |
| 氏名 | 松嶋 惇 | |
|---|---|---|
| 職名 | 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科 講師 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成21年) 医学博士(千葉大学) | |
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医 日本臨床細胞学会専門医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 |
| 氏名 | 井下 尚子 | |
|---|---|---|
| 職名 | 森山記念病院 病理診断科 部長 | |
| 出身校(卒業年) | 東京医科歯科大学(平成6年) 医学博士(東京医科歯科大学) | |
| 認定資格等 | 死体解剖資格 日本病理学会専門医・研修指導医 日本臨床細胞学会専門医・研修指導医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 人体病理学 下垂体腫瘍 |
診療実績
| 組織診 | 細胞診 | 術中迅速組織診 | 術中迅速細胞診 | 病理解剖 | |
| 2014年 | 7267 | 7072 | 142 | 267 | 6 |
| 2015年 | 7535 | 6509 | 144 | 235 | 7 |
| 2016年 | 7742 | 6544 | 168 | 250 | 5 |
| 2017年 | 7450 | 6722 | 133 | 240 | 4 |
| 2018年 | 7551 | 6763 | 166 | 203 | 3 |
| 2019年 | 7568 | 6744 | 176 | 200 | 10 |
| 2020年 | 6717 | 6217 | 106 | 197 | 4 |
| 2021年 | 7378 | 6245 | 127 | 193 | 2 |
| 2022年 | 7274 | 6165 | 90 | 200 | 3 |
| 2023年 | 7728 | 6194 | 113 | 212 | 1 |
| 2024年 | 7487 | 6043 | 112 | 165 | 2 |
2025年4月9日 定期更新実施